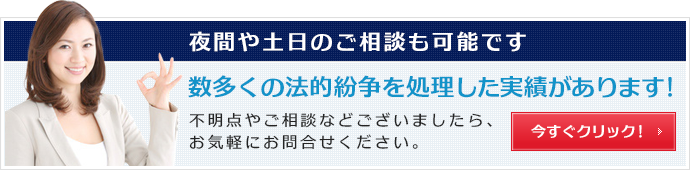周知商品等表示
著名商品等表示
商品形態模倣行為
営業秘密
技術的制限手段無効化装置等の提供行為
ドメイン名に係る不正行為
品質等誤認行為
信用毀損行為
代理人等の商標無断使用行為
周知商品等表示の混同惹起行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)
周知商品等表示の混同惹起行為については、不正競争防止法第2条第1項第1号において、不正競争の一類型として規定されています。
本条の趣旨は、他人の商品等表示として需要者間に広く知られているものと同一又は類 似の表示を使用して、その商品又は営業の出所について混同を生じさせる行為を規制することにより、周知商品等表示に化体された信用を保護し、事業者間の公正な競争を確保することにあります。
「商品等表示」とは、「商品の出所又は営業の主体を示す表示をいい,具体的には,人の業務に係る氏名,商号,商標(サービスマークを含む)等」(経済産業省 知的財産政策室 編「逐条解説 不正競争防止法 ~平成27年改正版~」)をいうとされております。「商品等表示」は、自他識別力又は出所表示機能を有するものでなければならず、表示が、単に用途や内容を表示するにすぎない場合には商品等表示に含まれないとされています。
「商品」とは、市場における流通の対象物となる有体物又は無体物をいいます。
「営業」とは、単に営利を直接の目的として行われる事業に限らず、事業者間の公正な競争を確保するという法目的からして、広く経済収支上の計算の上に立って行われる事業一般を含み、事業に営利性は要求されないので、非営利事業についても、経済収支上の計算の上に立って行われているものである以上は「営業」に該当すると解されています。
「需要者の間に広く認識されている」とは、必ずしも全国的に認識されていなくても、一地方であっても保護すべき一定の事実状態が形成されていればその限りにおいて保護されるべきと解されています。
「混同」については、現に混同が発生していることは必要でなく、混同を生じるおそれがあれば足りるとされています。「混同を生じさせる行為」には、被冒用者と冒用者との間に競業関係があり、直接の営業主体の混同を生じさせる「狭義の混同惹起行為」のみならず、緊密な営業上の関係や同一の表示を利用した事業を営むグループに属する関係があると誤信させるような「広義の混同惹起行為」も含むと解されています。
著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)
他人の著名な商品等表示の冒用行為については、不正競争防止法第2条第1項第2号において、不正競争の一類型として規定されています。
2条1項1号は、混同が生じているか、またはそのおそれがあることが必要ですが、2条1項2号では混同は要件ではありません。
これは、商品表示や営業表示が広められ著名になると、独自のブランド・イメージが顧客吸引力を有するようになり、個別の商品や営業を超えた独自の財産的価値を持つに至る場合があります。
このような著名表示を冒用する行為が行われると、たとえ混同が生じない場合であっても、冒用者は自らが本来行うべき営業上の努力を払うことなく著名表示の有している顧客吸引力に「ただのり」することができる一方で、永年の営業上の努力により高い信用・名声・評判を有するに至った著名表示とそれを本来使用してきた者との結びつきが薄められることになってしまいます。
平成5年改正で2号の規定が設けられるまでは、現実には混同が生じているかどうかは疑わしいのではないかと考えられる事案についても、著名である場合には、混同を認定することで事実上、著名表示の保護を図っていましたが、解釈論の限界を超えているのでは ないかとの指摘がなされていました。
著名表示の冒用行為については、著名表示の財産的価値が侵害されていることが問題なのであって、「混同」が生じているかどうかは必ずしも重要ではないと考えられることから、他人の著名な商品等表示の冒用行為について、混同を要件とすることなく不正競争の一類型とする本号の規定が設けられました。
2号が適用されるのは、著名な商品等表示を「自己の商品等表示として」使用した場合に限られ、他人の類似表示が物理的付されていても、出所表示機能を果たしていない場合には、2号には該当しません。
2号は、混同を要件とすることなく不正競争とするものであるので、単に広く認識されている程度でなく、「著名」であることが要件となっています。
どの程度知られていれば「著名」といえるかについては、個別具体的に判断される問題ですが、著名表示の保護が広義の混同さえ認められない全く無関係な分野にまで及ぶものであることから、通常の経済活動において、相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度にその表示が知られていることが必要で、具体的には全国的に知られているようなものを想定しているとされています。また著名表示と同一表示のみならず、著名表示が容易に想起できるような類似の表示も2号の対象となっています。
商品形態模倣行為
概要 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為(商品形態模倣行為)は、不正競争行為とされています(不正競争防止法2条1項3号)。
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為(商品形態模倣行為)は、不正競争行為とされています(不正競争防止法2条1項3号)。
3号の趣旨は、他人が商品化のために資金・労力を投下した成果を他に選択肢があるにもかかわらずことさら完全に模倣して、何らの改変を加えることなく自らの商品として市場に提供し、その他人と競争する行為は、競争上、不正な行為として位置づけられる必要があるからであるとされています(逐条解説不正競争防止法64頁)。
商品形態は、通常意匠法により保護されるのが原則ですが、意匠登録には時間と費用がかかり、商品サイクルが早い分野では意匠登録により権利保護を図るのは現実的ではないケースがままあります。そのような場合は、デッドコピー規制として、不正競争防止法により商品形態模倣行為を抑止するメリットがあります。
商品の形態「商品の形態」とは、「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」と定義されています(不競法2条4項)。
上記定義から、「商品の形態」とは具体的な形状等を意味しており、抽象的な商品のアイデアは含まれません。
(1)商品内部の形態上記のように、「商品の形態」の定義が、「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識 することができる商品の外部及び内部の形状」とされている以上、商品内部の形態については原則として保護を受けません。しかし、通常の使用時に、需要者に外部から容易に認識され、需要者に注目される場合は、商品内部の形態であっても保護されることになります。
(2)セット商品セット商品の組み合わせ自体はアイデアに過ぎませんので、商品形態には該当しません。しかし、セット商品の外観については、組み合わされたセット自体を一つの商品と考えることができますので、商品形態に該当するとも考えられます。
小熊タオルセット事件(大阪地判平成10年9月10日知的裁集30巻3号501頁)は、小熊の人形やタオル類等を包装箱等に収納したセット商品全体の形態を中心に、「商品の形態」を捉えています。
その他、宅配鮨事件(東京地判平成13年9月6日判時1804号117頁)でも、一般論として、使用する容器、ネタ及び添え物の種類、配置等によって構成されるところの1個1個の鮨を超えた全体としての形状、模様、色彩及び質量感などが商品の形態となり得ると判示しています。
(3)商品の容器・包装商品の容器・包装が「商品の形態」と言えるかは、定義上明らかではありません。
この点、ワイヤーブラシセット事件(大阪地判平成14年4月9日判時1826号132頁)では、商品の容器や包装についても、商品と一体となっていて、商品自体と容易に切り離せない態様で結びついている場合には、同号の「商品の形態」に含まれるとしたうえで、包装(台紙及びブリスターパック)も「商品の形態」に含まれると判示しました。
模倣不正競争防止法2条5項では、「模倣」とは、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう」と定義されています。
「依拠」とは、「当該他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していること」とされています(ドラゴンキーホルダー事件(東京高判平成10年2月26日知的裁集30巻1号65頁)。
また、上記東京高判は、「実質的同一性」について、「他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に、形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似していること」を意味するとしています。
「依拠」とは「依拠」とは、「他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していること」とされています(ドラゴンキーホルダー事件(東京高判平成10年2月26日判時1644号153頁))。
このように、「依拠」したといえるか否かは、主観面が問題となるので、依拠性が訴訟で争われた場合、それをどのような方法で立証していくかが大きな問題となります。この点は、著作権侵害事件における依拠性の立証と類似するものといえます。
(1)アクセス可能性被告が原告商品にアクセスすることができた状況であれば、アクセス可能性があるといえます。例えば、原告商品の販売時期の方が被告商品の販売時期より先行している事実、両商品の販売エリアが重複している事実、原告商品の市場での認知度が相当高かった事実等の間接事実を、原告は証明することになります。
(2)商品形態の類似性被告商品の形態が原告商品の形態と偶然似てしまったような場合であれば、依拠性は認められず、形態模倣行為に該当しないことになります。しかし、単純な形態であればともかく、それなりに個性がある商品形態の場合、殆ど同じ形態の商品が偶然に作り出されるとは通常考えられず、両商品の形態が似ていれば似ているほど、依拠性は認められやすいといえます。
(3)開発の時間的前後関係被告商品の方が原告商品よりも先に開発していたという事実が証明された場合、被告商品が原告商品に依拠していないことを示す間接事実となり得ます。
形態の実質的同一性「模倣」のもう一つの要件として、原告商品に依拠して作成された被告商品の形態が、原告商品の形態と実質的に同一であることが必要です。実施的に同一であるか否かは、原告商品と被告商品の形態を対比して、その共通点がありふれたものであるか否か、創作的なものであるか、他方相違点は些細なものであるか否か等の観点から、総合的に判断されます。
なお、上記実質的同一性について、需要者を基準に判断するのか、競業者を基準に判断するのか争いがありますが、裁判実務でも明確にはなっていません。
営業秘密
営業秘密とは 近年の経営戦略において営業秘密は注目されています。不正競争防止法において保護される営業秘密については第2条1項4号~9号に規定されております。
近年の経営戦略において営業秘密は注目されています。不正競争防止法において保護される営業秘密については第2条1項4号~9号に規定されております。
不正競争防止法により保護を受けられる営業秘密には3つの構成要件が必要とされています。
3つの構成要件とは【1】秘密管理性、【2】有用性、【3】非公知性の3つになります。
まず1点目の秘密管理性とは、営業秘密が秘密として管理されていることをいいます。これまでの判例では、秘密管理性があると認められるには【1】アクセス制限が課されていること及び、【2】客観的に秘密であることが認識できることが必要とされております。つまり、営業秘密として保護を受けたいのであれば、パスワード管理や施錠管理をしたり、「極秘」の印を押すなどの情報管理が必要となります。
2点目の有用性とは、事業活動に役立つ情報であるという意味です。特許法で保護を受けることができる製法等の技術情報以外にも、顧客名簿や仕入れ先リスト、実験の失敗データや、接客マニュアル等の情報も事業活動に有用なものであれば保護を受けられます。特許法、実用新案法等で保護を受けるには、保護を受ける代償として技術情報の公開をする必要がありますが、他社に解析できないような情報であれば営業秘密で保護を受けるというのも良い選択肢となり得ます。
3点目の非公知性とは、情報を保有管理する以外の者が当該情報を一般的には入手することができない状況にあることをいいます。
上述した3つの構成要件を全て満たし、不正競争防止法2条1項4号~9号に該当する行為をされた場合は、原則として不正競争防止法上の保護を受けることができます。
ただし、営業秘密の不正競争防止法上の保護には、消滅時効(15条)があり、また適用除外規定(19条)があるので権利行使をする際には注意が必要です。
営業秘密に係る不正競争行為の各類型について営業秘密に係る不正競争行為については2条1項4号から9号で規定されています。
4号は、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) 」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体例としては、従業員がカギを盗んで施錠管理された保管庫から顧客リストを取得する行為等が該当します。
5号は、「その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体例としては、従業員が不正取得した顧客リストであることを知りながら産業スパイが顧客リストを買い取るような行為が該当します。
6号は、「その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。「その取得した後に」とあるのは営業秘密の取得時には善意又は無重過失であったが、その後悪意者等に変わっていることが必要であることを意味しています。具体的には、営業秘密取得時は産業スパイ活動があったことを知らなかったが、営業秘密を取得後に報道等で産業スパイ活動があったことを知り、それにも拘わらずその営業秘密を使用した場合などは6号に該当します。
7号は、「営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体的に「不正の利益を得る目的」とは、営業秘密の保有者が従業員、ライセンシーなどに営業秘密を開示した場合に、従業員等が金銭目当てで産業スパイなどに営業秘密を売ることなどが該当します。「保有者に損害を加える目的」とは、財産上の損害の他にも、信用の失墜やそのほかの有形無形の不当な損害を加える目的であることを意味し、実際に損害が発生しているかどうかは問われません。
8号は、「その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」が不正競争行為に該当することを規定しています。具体的には、営業秘密の取得時に、営業秘密の保有者の従業員が不正の利益を得る目的で産業スパイに開示した顧客リストであることを知りながらその顧客リストを産業スパイから購入した場合などは本号の類型に該当します。
9号は、「その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体的には、営業秘密の取得時には不正開示行為があったことを知らなかったが、営業秘密を取得したのちに、営業秘密の保有者から警告書が送られてきて不正開示行為があったことを知ったにも関わらずその営業秘密を使用したり、他人に開示した場合は本号の類型に該当します。
2条1項4号から9号に該当する場合、事業者は差止請求権、損害賠償請求権、信用回復措置請求権を行使することができます。
尚、19条1項6号において「取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為」については適用除外となる旨が規定されており、19条1項6号に該当する場合は差し止め請求権等の行使はできません。
また、営業秘密については不正競争防止法第21条第1項第1号から第7号までにおいて「営業秘密侵害罪」が規定されておりこれらに該当する場合は、刑事上の保護が受けられます。
営業秘密管理指針経済産業省から「営業秘密管理指針」が出されています。不正競争防止法を所管しているのが経済産業省ですので、法的拘束力を持つものではありませんが、裁判実務でも参考にされていますし、裁判例を踏まえた上で指針が作成されていますので、営業秘密の管理をきちんと行おうとしている企業にとっては、その内容を十分理解しておく必要があるでしょう。
なお、営業秘密管理指針は、平成15年1月に策定されたのですが、平成27年1月に全面改定されました。従来の営業秘密管理指針は、情報管理に関するベストプラクティス及び普及啓発的内容を多く含んでいたため、大企業でもそれを理解実施するのは困難で、中小企業にとっては到底実施不可能な内容も記載されていました。
そのような批判を受けて、新しい営業秘密管理指針は、不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示したものです。本来あるべき営業秘密の漏えい防止策ないしは漏えい時に推奨される(高度なものを含めた)包括的対策は、別途「営業秘密保護マニュアル」(仮称)が出される予定です。
営業秘密管理指針については、経済産業省のホームページからご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf
不正競争防止法 平成27年改正のポイント1 営業秘密侵害品関連条1項10号(新設条文)第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)
⇒従前は、生産方法の営業秘密などを使用した場合に生じるいわゆる営業秘密侵害品についての譲渡・輸出を規制する条文がありませんでした。そこで、営業秘密侵害品であることを知って、又は重大な過失により知らないで譲渡等の行為をすることを禁止する条文が新設されました。
21条1項9号(新設条文)不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号若しくは第四号から前号まで又は第三項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号及び次条第一項第二号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)
⇒営業秘密侵害品の譲渡行為等に関する刑事罰の条文もあわせて新設されました。
刑事罰については、行為者が「知っている」場合だけが対象となり、過失犯は対象となりません。
不正競争防止法 平成27年改正のポイント2 営業秘密の転得者処罰の範囲拡大21条1項8号不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第二号若しくは第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪(第二号及び第四号から前号までの罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
⇒旧法下においては、最初の開示者から情報開示を受けた者(いわゆる第2次開示者)までが刑事罰の対象となっていましたが、近年はIT技術の発展に伴い、営業秘密の多くが電子化されており、外部へのデータ持ち出しが容易になり、漏えいした営業秘密が転々流通される危険性が高くなっており、第2次開示者までを処罰するのみでは、十分な保護ができているとは言い難い状況となってきました。今回改正では、第3次取得者以降であっても不正開示がなされた営業秘密であることを知って、使用又は開示した場合は刑事罰の対象としました。
不正競争防止法平成27年改正のポイント3 国外犯処罰の範囲拡大21条6項(改正)第一項各号(第九号を除く。)、第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号に係る部分を除く。)の罪は、日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
⇒旧法下では、国外で行われた営業秘密侵害については、不正使用行為及び不正開示行為のみが刑事罰の対象となっておりました。しかしながら、最近ではクラウドなどのように物理的には日本国外のサーバーにおいて営業秘密が管理されている場合などもあり、このような営業秘密が国外において不正取得された場合に処罰の対象となるのかが不明確でした。
そこで、「日本国内において事業を行う保有者の営業秘密」が国外犯の処罰の対象となることを明確にするため条文の改正を行いました。
不正競争防止法平成27年改正のポイント4 罰則強化等による抑止力の向上21条1項柱書(改正)次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲 役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⇒個人の営業秘密侵害罪の罰金金額が、1,000万円から2,000万円に増額され、罰則が強化されました。
21条3項(新設)次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者
二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三 日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者
⇒国外使用目的で営業秘密を取得等した個人に対し、重罰化する規定が設けられました。
21条10項(新設)次に掲げる財産は、これを没収することができる。
一 第一項、第三項及び第四項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二 前号に掲げる財産の果実として得た財産、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他同号に掲げる財産の保有又は処分に基づき得た財産
⇒営業秘密侵害行為によって犯人が、罰金金額を超える莫大な利益を得るということが生じるようになり、罰金による抑止力が効かないようなケースも考えられるようになりました。そこで、個人及び法人が営業秘密侵害行為により得た収益について上限なく没収できる規定が新設されました。
22条1項(改正)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 前条第三項第一号(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)若しくは第三号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)又は第四項(同条第三項第一号(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第三号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。) 十億円以下の罰金刑
二 前条第一項第一号、第二号、第七号、第八号若しくは第九号(同項第四号から第六号まで又は同条第三項第三号(同条第一項第四号から第六号までに係る部分に限る。)の罪に係る違法使用行為(以下この号及び第三項において「特定違法使用行為」という。)をした者が該当する場合を除く。)又は第四項(同条第一項第一号、第二号、第七号、第八号及び第九号(特定違法使用行為をした者が該当する場合を除く。)に係る部分に限る。) 五億円以下の罰金刑
⇒22条1項1号は、国外使用目的で営業秘密を取得等した法人に対し、重罰化する規定です。22条1項2号は、営業秘密を不正に使用等した法人に対する罰金を3億円から5億円へと重罰化したものです。
技術的制限手段無効化装置等の提供行為
技術的制限手段に対する不正行為は、不正競争防止法第2条第1項第11号、第12号で規定されています。
不正競争防止法における「技術的制限手段」の定義については、第2条第7項で、「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう」とされています。
コンテンツ提供事業者は、コンテンツを利用する人から利用料金等を得ることによってビジネスをしているので、無断コピーや無断アクセスができないようにコピー管理技術、アクセス管理技術を用いています。しかしながら、これらを無効化してコンテンツを利用しようとする者がいます。もちろんコンテンツ提供事業者も管理技術の高度化をしていますが、無効化技術のほうも進歩しており、鼬ごっこ状態です。
このような状況を踏まえて、コンテンツ提供事業者の競争秩序を維持するという観点から、平成11年改正で、技術的制限手段に対する不正行為を不正競争の一類型として規制することになりました。
しかしながら、その後も技術的制限手段に関する不正行為は、後を絶たなかったため、平成23年改正において強化されました。
11号は、「営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置若しくは当該機能を有するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」を禁止するものです。
11号の対象となるのは、記録媒体や視聴機器の購入者、所持者の全員が対象となるような技術的制限手段が施されたもので、具体的には、映画のBDやDVD等の記録媒体にコンテンツとともに制御用の信号を組み込んでコピーできないようにしたものや、特定のゲーム機本体と組み合わせないと実行できない信号を組み込んだゲームソフトに対して、これらの技術効果を無効化するキャンセラー等を販売するような行為です。
12号は、「他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために 営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置若しくは当該機能を有するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に 譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」を禁止するものです。
12号の対象となるのは、営業上の利益を確保することを目的として、音楽、映像等のコンテンツ提供事業者が、契約の相手方または契約により特定された者以外の者によるコンテンツの視聴、記録を制限するために「技術的制限手段」を用いている場合に、その技術的制限手段の「効果を妨げる」機能を有する装置等を譲渡等する行為です。
具体的には、有料の衛星放送やケーブルテレビ等で契約者以外の者がスクランブルを解除できないような暗号を施している場合に、この技術効果を無効にする解除装置を販売等する行為が該当します。
ドメイン名に係る不正行為(不正競争防止法2条1項13号)
ドメイン名に係る不正行為の趣旨不正競争防止法2条1項13号は、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を「不正競争」の一類型としています。
ドメイン名は、原則として誰もが先着順に登録できる制度になっており、登録に際して、実質的な審査は行われません。そのため、第三者が有名企業や著名な商品の名称と同一又は類似したドメイン名を登録して、フリーライドしてウェブサイト上でビジネスを行ったり、取得したドメイン名を不当に高く買い取らせるような事例が多くなっており、このような行為を規制する必要から本規定が設けられました。
「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」不正競争防止法2条1項13号では、主観的要素として、「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」(図利加害目的)が規定されています。これは、保護対象に周知性や著名性が要求されず、ドメイン名の使用行為に限らず取得、保有行為も対象とされていることから、主観面で限定を図る必要があるためです。
図利加害目的が認められる行為の例は、以下のような行為です。
①特定商品等表示の使用者がその特定商品等表示をドメイン名として使用できないことを奇貨として、当該特定商品等表示の使用者に不当な高額で買い取らせるために、当該特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を先に取得・保有する行為
②他人の特定商品等表示を希釈化・汚染する目的で当該特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名のもと、アダルトサイトを開設する行為
「特定商品等表示」「特定商品等表示」とは「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの」を指します。
「同一又は類似」規制の対象となるドメイン名は、他人の特定商品等表示と「同一又は類似」のものです。
「ドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」「ドメイン名を使用する権利」とは、ドメイン名登録機関に対してドメイン名を請求できる権利を指します。
ドメイン名を使用する権利を「保有」する行為には、ドメイン名を使用する権利を継続して有することを指します。
ドメイン名を「使用する行為」とは、ドメイン名をウェブサイト開設等の目的で用いる行為を指します。
品質等誤認行為
品質等誤認惹起行為については、不正競争防止法第2条1項14号で規定されています。
商品・役務の原産地等について誤認を生じさせるような表示を放置すれば、適正に表示している競業他社は不利益を被ることになりますので、このような行為は不正競争行為であるとしています。
具体的には、実際は豚肉と鶏肉も入っているのに「牛肉100%」と表示したり、中国産のうなぎを「静岡県産」と表示したり、清酒の等級を偽ったりするのは、本号に該当する可能性があります。
本号の対象となる表示物は、「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信」です。
ここでいう「取引に用いる書類」とは、注文書、見積書、送り状、計算書、領収書等を指し、取引に用いる「通信」とは、取引上現れる表示行為中書類以外の通信形態の一切のものを指します。
本号の対象となる表示内容は、「商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量について誤認させるような表示」、又は「役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示」です。
ここでいう「原産地」とは、商品が生産、製造された場所だけでなく、商品が加工され商品価値が付与された地も含みます。
ここでいう「製造方法」とは、商品の製造に用いられる方法をいい、例えば醤油であれば本醸造方式などがあります。
ここでいう「用途」とは、商品の特徴に応じた使い途をいいます。
本号の対象となる行為は、品質等誤認をさせる「表示」をする行為、又は「その表示をした商品を譲渡し,引き渡し, 譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入」する行為、「電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為」です。
本号の民事上の請求主体は、本号の誤認惹起行為によって「営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者」で、競業相手でない一般消費者には原則として請求主体性が認められないとされています。
信用毀損行為
信用毀損行為については、不正競争防止法第2条第1項第15号で不正競争行為として規定されています。
競業他社の信用を毀損するような虚偽事実を流布することを放置すれば、虚偽の事実を流布された者は営業上の信用を害され、不利な立場に置かれることになり、競業秩序を乱すことになりますので、本号で禁止されているのです。
本号の適用には、競争関係があることが必要です。ここでいう「競争関係」とは、「双方の営業につき,その需要者又は取引者を共通にする可能性があること」をいいます(逐条解説 不正競争防止法 - 平成27年改正版 -)。
また、信用を害されている「他人」が誰であるかが、特定されている必要があります。この「他人」については、明示されていなくても告知内容及び業界内での周知情報から誰であるか取引者がこの「他人」が誰であるかを特定できるのであれば、それで足りるとされています。
ここでいう「虚偽の事実」とは、客観的真実に反する事実のことをいいます。
ここでいう「告知」とは、自己の関知する事実を、特定の人に対して個別的に伝達する行為をいい、例えば、競業他社の商品は粗悪品で、すぐ故障する等と伝えるような行為が該当します。
ここでいう「流布」とは、事実を不特定の人又は多数の人に対して知られるような態様において広める行為をいい、例えば業界誌等に競業者の商品を誹謗する記事を掲載するような行為を指します。
尚、特許権等の知的財産権の権利侵害において、権利侵害の事実や訴訟提起の事実の告知を相手方の取引先に対して行うことは、正当な訴訟活動行為の一環であると認められる場合は、違法性は阻却されるとされていますが、権利が有効でないのが明白なのにこのような告知をした場合は、本号に該当する可能性があります。
又、本号が規定する信用毀損行為については、当事者間の民事的請求に委ねられており、刑事罰の対象とはされていません。
代理人等の商標無断使用行為
外国において、商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者による商標冒用行為については、不正競争防止法第2条第1項第16号で不正競争行為の一類型として規定されています。
本規定は、パリ条約第6条の7第2項に対応するために、昭和40年の法改正で導入された規定です。
商標権は、属地主義の原則に則り、登録国においてのみ効力を有するのが大前提ですが、国際的に「不正競争」を禁止するという観点から本件規定が設けられました。
具体的には、外国において、商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者が正当な理由もないのに、外国において権利を有する者の承諾を得ないで、勝手に商品等に当該商標を使用した場合などが該当します。
ここでいう外国とは、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約締約国を指します。
商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者については、現在の代理人等だけでなく、その行為の日前1年以内に代理人又は代表者であった者も含まれます。
尚、本号は刑事罰の対象とはされていません。