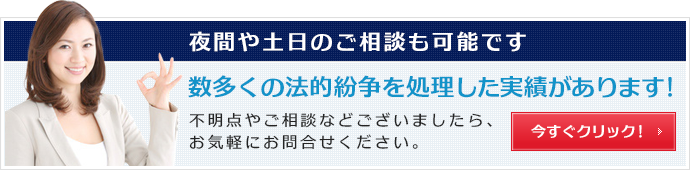原告は、各種娯楽機械の輸出入、製造、販売、賃貸その他を主たる営業の目的とする会社で、テレビ型ゲームマシン(商品名スペース・インベーダー、以下、「原告商品」という。)を、国内七〇か所に所在する営業所及び出張所並びにオペレーター(卸売業者)を介して、ゲーム場、喫茶店その他の需要者に販売又は賃貸し、あるいは国内各所に所在する原告の直営するゲーム場において一般の入場者の使用のために展示している。
被告会社は、テレビ型ゲームマシンの製造、販売及び賃貸等を営業の目的として設立された会社で、商品名を「フアイテイング・ミサイル」とするテレビ型ゲームマシン(以下、「被告商品」という。)を製造、販売及び賃貸していました。
原告は、被告の行為は不正競争行為に当たるとして損害賠償請求を行いました。
東京地裁は、「(原告商品の)受像機に映し出されるインベーダーを主体とする各種影像とゲームの進行に応じたこれら影像の変化の態様の前記特殊性及び新規性が出席した業界関係者の注目を浴び、昭和五三年中において、業界紙、専門誌、新聞等に多数回にわたり紹介されるとともに、原告によつて、業界紙、パンフレツト等により継続的な宣伝活動がされた。...原告商品の受像機に映し出される前記インベーダーを主体とする各種影像とゲームの進行に応じたこれら影像の変化の態様は、それ自体、商品の出所を表示することを目的とするものではないが、遅くとも昭和五四年一月初めころには、取引上二次的に原告商品の出所表示の機能を備えるに至つたものと認められるのであつて、(旧法)不正競争防止法第1条第1項第1号の規定にいう『他人ノ商品タルコトヲ示ス表示』として、そのころ我が国において周知になつたものということができる。被告商品はSPACE MISSILEと表示されている点が相違するのみで、他は全く同一であることが認められ、...被告会社が被告商品を製造販売及び賃貸する行為は、被告商品を原告商品と混同させるものというべきである。」として被告の行為は不正競争に該当すると判断しました。
スペース・インベーダー事件 東京地裁昭和57年9月27日判決
つきたて事件 京都地裁昭和57年4月23日判決
原告の前身である会社は「つきたて」なる表示の電気餅つき機を昭和四六年ころから売り出していました。
一方、被告のほうも昭和四八年ころから「つきたて」なる表示の電気餅つき機を販売していました。
原告は、不正競争防止法に基づき、被告に対して差止請求、損害賠償請求訴訟を提起しました。
京都地裁は、「原告の商品に標章された『つきたて』なる表示は、電気餅つき機の効能を表現・連想させるに止り、商品の個別的識別機能すなわち、特別顕著性を有しない。...原告の『つきたて』なる表示の永年使用による個別化を具有するに至つたともいえない。」として原告の請求を棄却しました。
iMac事件 東京地決平成11年9月20日
債権者は半透明の白と青のツートンカラーのプラスチック素材を使用したパソコン「iMac」を製造販売しています。債務者がこれに類似するパソコンを製造販売しているため、債権者は、不正競争防止法2条1項1号に基づき、その差止を請求しました。
東京地裁は、「債権者商品は、パーソナルコンピュータとしては、従前、類似の形態を有する商品がなく、形態上、極めて独創性の高い商品ということができる。そして、債権者商品について、その形態に重点を置いた強力な宣伝がされたこと、債権者商品は、その形態の独自性に高い評価が集まり、マスコミにも注目され、販売実績も上がり、いわゆるヒット商品になっていることが一応認められる。以上によれば、債権者商品の形態は、債権者らの商品表示として需要者の間に広く認識されている(周知商品表示性を獲得している)ものというべきである。」として債権者の主張を認め、仮処分の決定をしました。
スナックシャネル事件(最高裁平成10年9月10日第一小法廷判決)
X(原告・被控訴人=附帯被控訴人・上告人)は世界的に有名な高級服飾グループの「シャネル・グループ」に属し「シャネル」の表示について商標権等の知的財産権を有し、その管理をおこなっているスイス法人です。
Y(被告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は千葉県松戸市内の賃借店舗において「スナックシャネル」の営業表示を使用し、サインボードにこれを表示して飲食店を開店しました。
Xは「Yは、その営業上の施設又は活動に『シャネル』又は『シャレル』その他『シャネル』に類似する表示を使用してはならない」とする差止請求及び損害賠償を請求しました。一審の松戸地裁ではXの差止請求と損害賠償請求の一部を認めましたが、Xが控訴、Yが附帯控訴しました。二審の東京高裁では、Yの営業の種類、内容及び規模等に照らすとYが本件営業表示を使用してもシャネル社の営業上の施設等と混同を生じるおそれはないとしてXの請求を棄却し、Yの付帯控訴を容れた為、Xは上告しました。
最高裁は、「新法二条一項一号に規定する『混同を生じさせる行為』は、右判例が旧法一条一項二号の『混同ヲ生ゼシムル行為』について判示するのと同様、広義の混同惹起行為をも包含するものと解するのが相当である。けだし、(一)旧法一条一項二号の規定と新法二条一項一号の規定は、いずれも他人の周知の営業表示と同一又は類似の営業表示が無断で使用されることにより周知の営業表示を使用する他人の利益が不当に害されることを防止するという点において、その趣旨を同じくする規定であり、(二)右判例は、企業経営の多角化、同一の表示の商品化事業により結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業を取り巻く経済、社会環境の変化に応して、周知の営業表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同惹起行為をも禁止することが必要であるというものであると解されるところ、このような周知の営業表示を保護する必要性は、新法の下においても変わりはなく、(三)新たに設けられた新法二条一項二号の規定は、他人の著名な営業表示の保護を旧法よりも徹底しようとするもので、この規定が新設されたからといって、周知の営業表示が保護されるべき場合を限定的に解すべき理由とはならないからである。これを本件についてみると、被上告人の営業の内容は、その種類、規模等において現にシャネル・グループの営む営業とは異なるものの、「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、シャネル・グループの属するファッション関連業界の企業においてもその経営が多角化する傾向にあること等、本件事実関係の下においては、被上告営業表示の使用により、一般の消費者が、被上告人とシャネル・グループの企業との間に緊密な営業上の関係又は同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信するおそれがあるものということができる。したがって、被上告人が上告人の営業表示である「シャネル」と類似する被上告人営業表示を使用する行為は、新法二条一項一号に規定する「混同を生じさせる行為」に当たり、上告人の営業上の利益を侵害するものというべきである。」として破棄戻しとしました。
本判決は2条1項1号の「混同」に「広義の混同」が含まれることを明確にしている点で注目すべき判決と言えるでしょう。
泉岳寺事件(東京高裁平成8年7月24日判決)
本裁判例は、不正競争防止法2条1項1号の混同についての判断が示された高裁判決です。Y(東京都-被告・被控訴人)は昭和43年に都営地下鉄浅草線の駅名として「泉岳寺」を告示し、同年に開業以来その駅名をずっと使用してきました。X(宗教法人泉岳寺-原告・控訴人)は、不正競争防止法2条1項1号、法人の氏名権(名称権)などを理由として「泉岳寺」の駅名使用の差止を求めた事件です。原審では宗教法人が都営地下鉄事業を行うことは一般的にありえないこと等から混同を生ずるおそれはないとしてXの請求を棄却しました。これを不服としてXが控訴したというものです。 東京高裁は以下のように判事しました。「都営地下鉄事業は、地方公営企業法に基づき、地方公共団体であるYが行う事業であって、(省略)Xのような宗教法人が都営地下鉄事業を行うことは法的にありえないことであり、仮にX主張のように宗教法人としてのXの行う関連事業が同法(不正競争防止法2条1項1号)の営業にあたる場合があるとしても、このXの行う営業とYの行っている都営地下鉄事業とは明白に区別できる別種の営業とみられるものであるから、一般人が、Yの本件駅名使用行為により泉岳寺駅の営業ないし都営地下鉄浅草線の地下鉄事業をXないしその関連企業による営業と誤認し、あるいはXとYとが何らかの経済的、組織的関連があると誤認することは通常考えられず、したがって『泉岳寺』との名称が著名であることを考慮に入れても、広義の混同を含め営業の混同を生ずるおそれがないことは明らかである。」としてXの控訴を棄却しました。 不正競争防止法上の混同については、営業上の混同を生ずるか否かで判断することとなります。この高裁判決では、駅である「泉岳寺」を表示する営業主体が都営地下鉄となっていますから、営業主体が東京都であることは明らかですし、「泉岳寺」の営業主体は宗教法人であることは明らかですから、いくら「泉岳寺」が著名な寺であるからといって混同を生じるとは考えにくいので高裁の判決は妥当だと思われます。
日本ウーマン・パワー事件(最高裁昭和58年10月7日第二小法廷判決)
本事件は、不正競争防止法2条1項1号(旧法1条1項2号)の類似・混同について最高裁が判断を示した事例です。
X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和41年11月に設立され、「マンパワー・ジャパン株式会社」の商号(以下「X商号」とする)およびその通称である「マンパワー」(以下「X通称」とする)という名称を用いて事務処理請負業を営んでいました。Y(被告・控訴人・上告人)は、昭和51年4月に設立され、Xと同様に事務処理請負業を「日本ウーマン・パワー株式会社」の商号(以下「Y商号」とする)を用いて行っていた。
Xの商号及びその通称はYの設立登記が行われた頃には、Xの本店、支店及びその周辺地域でXの営業活動を示す表示として広く認識されていました。そしてXにはXとYが同一営業主体であると誤解したYの顧客から電話がかかってきたり、Xの顧客から「YはXの子会社か」等の問い合わせを受けたことがあったそうです。そこでXがYに対して旧不正競争防止法1条1項2号(現行の不正競争防止法2条1項1号)に基づきYによるY商号の使用差し止めとY商号の抹消登記請求を求めました。第1審、第2審ともにXの請求が認容されたため、Yが上告したというものです。
最高裁の判決のポイントは以下の通りです。
ポイント1:「ある営業表示が不正競争防止法1条1項2号(現行の不正競争防止法2条1項1号)にいう他人の営業表示と類似のものか否かを判断するに当たつては、取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする。」
ポイント2:「不正競争防止法1条1項2号(現行の不正競争防止法2条1項1号)にいう『混同ヲ生ゼシムル行為』は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である。」
ポイント1では、旧法1条1項2号(現行の不正競争防止法2条1項1号)の商品等表示の類否判断基準を示しています。
ポイント2では、旧法1条1項2号(現行の不正競争防止法2条1項1号)の混同には、狭義の混同のみでなく広義の混同を含む旨が判断されています。
本件では、「マンパワー」と「ウーマン・パワー」は、いずれも人の能力、知力を連想させること、「ジャパン」と「日本」の部分はいずれも観念において同一であることなどから類似であると判断され、営業表示として類似のものを使用しているからYはXの営業活動と混同を生じさせる行為をしたとしてYの上告は棄却されました。